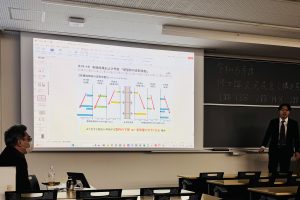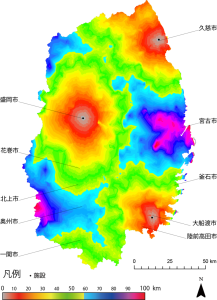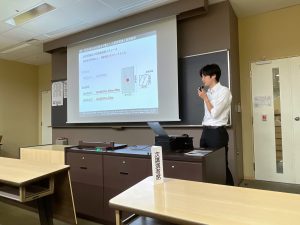材料・施工技術開発への関わり
私は2024年度までの約20年間、ゼネコンの研究所で構造材料(主にコンクリート)とその施工方法に関する技術開発・適用に携わってきました。ただし、大学院まではれんが造の研究を行っていたため、コンクリートの研究に触れたのは大学院2年生になってからです。就職後を考えて、当時ゼネコンが開発を競っていた超高強度コンクリートを研究室で練ってもらったのですが、練混ぜ用のミキサは唸りを上げ、出来上がったコンクリートはスコップも刺さらないほど固いという状況でした。コンクリートの強度を上げるためにはセメントを増やす必要があり、片栗粉を多量に混ぜた水のように粘性が高く、本当に使える材料なのかと強い不安を感じたのを覚えています。一方、就職後に見た超高強度コンクリートは特殊な剤を使用することで比較的扱いやすく、技術開発のすばらしさを実感した瞬間でした。

超高強度コンクリートの練混ぜ状況
建築生産の観点から考える
本研究室名にもある建築生産とは単なる施工ではなく、設計者・施工者・材料供給者などの協業による生産活動と考えます。例えば、設計者が超高強度コンクリートを使用することで柱の本数を抑えて自由度の高い空間を要望する場合、その施工や材料供給(製造)を可能にする技術開発が必要です。また、超高強度コンクリートは製造に時間がかかるため材料供給者からの供給量に対する制約が生じた場合、施工者は事前に工場で部材を製造しておいて工事現場で接合するプレキャスト化工法を、さらに設計者は構造性能確保などの観点からその接合方法について検討する必要があります。
このように、よい建物の建設のためには、設計・施工・材料などの技術を個別に考えるだけでなく、それらを一繋ぎにする建築生産の観点からのアプローチが重要と考えます。つまり、あなただけの活躍でよい建物は造れませんが、あなたの活躍はその建物の価値に確実に反映されると言えるのではないかと思います。私も国立競技場などの多くの地図に残る建物の建設に携わってきましたが、それらの建物に貢献したと誇りに思いながら仕事ができることは技術者にとって幸せなことだと思います。だから建築は面白い。

超高強度コンクリートを柱に使用することで得られた自由度の高い空間